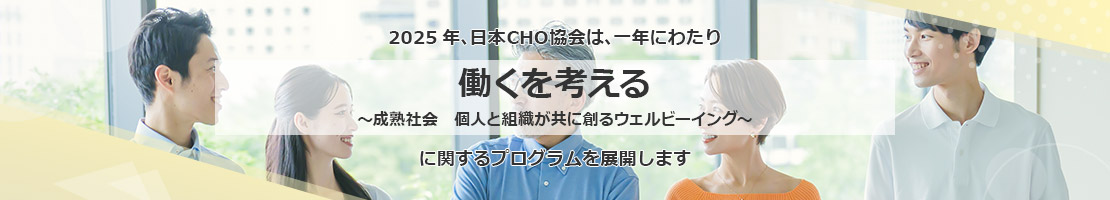

明日の経営と人事のあり方を考える日本CHO協会は、人事/人材開発に関する様々なテーマを取り上げ、「人事戦略フォーラム」、「人事実践セミナー」、「ダイバーシティ研究会」という3つの定例プログラムや、「CHOネットワーキングサービス」「DE&I共創コミュニティ」等少人数での情報交換会等を開催しています。
2025年1月現在、約750社/1,700名の人事部門幹部の皆様が会員登録され、上記プログラムは、学びの場・交流の場として毎回多くの方々が参加されています。
また、定例プログラムとは別に、一年間を通じた「年間重点テーマ」を設定し、
2019年は「シニア人材の活躍」
2020年は「人事部門の未来図 ~次世代型人事部門への進化~」
2021年は「“自律型人材”が求められる時代の人材開発/人材育成」
2022年は「ミドル・シニアのキャリア自律」
2023年は「人的資本経営の実践と人的資本の最大化」
2024年は「DE&Iが切り拓く未来」
を取り上げ、各年のテーマにもとづく様々なプログラムをご提供してきました。
2025年は『働くを考える』を、年間重点テーマに取り上げます。
昨年、日本はドイツに抜かれGDP世界第4位に落ちました。さらに今年は世界一の人口を持つインドの躍進で第5位に転落する見込みです。
国民総生産という量を追い求める時代から、質を求める成熟社会に移行する中で、「働く」ことの意味を改めて考えなおす時期に来ているのではないでしょうか?
時代をさかのぼれば、古代ギリシャでは労働は神の罰としての苦役であり、働かない貴族が理想の生き方とされていました。その後16世紀の宗教改革以降、与えられた仕事に励むことが神に喜ばれること、「calling」(天職)という概念が生まれます。
社会学者マックス・ヴェーバーは、資本主義の精神の萌芽を、この清教徒的倫理感にあると考察し「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を著しました。
その後、職業倫理は宗教から切り離され、工場労働による人間疎外が社会問題化していく中で、カール・マルクスは共産主義を唱えます。
第二次世界大戦後、資本主義国家の労働者の大半は、組織に雇われる給与所得者となり、その労働観は「悪くない給料とまずまずの年金、そして自分と限りなくよく似た人達の住む快適な地域社会に、そこそこの家を与えてくれる仕事に就こうとする」(ウィリアム・H. ホワイト『組織の中の人間-オーガニゼーション・マン』)ものとなり、日本もその例外でなく会社第一のモーレツ社員が高度経済成長を支えました。
そして現在の日本、「人生100年時代」から「100年現役社会時代」へ、生涯働けるまで働き続けることが求められる中で、働く意義・目的は「自己実現」「社会貢献」など「生きがい」をもたらすものへと変化しています。今後、ますます『働く』ことで得られる充実感や達成感が、個人のウェルビーイングを高め、組織全体の活力にも繋がるようになります。
そのような背景を踏まえ、2025年の日本CHO協会は、様々な角度から『働く』を再考する場を設定します。
そして皆様と共に、ウェルビーイング(働く幸せ)、組織と個人が共に創る幸せな社会の実現を目指して参ります
個別のプログラムは、詳細が決定し次第、順次ご案内いたしますので、ぜひ奮ってご参加ください。また皆様の関心の高いテーマも随時取り上げますので、具体的なご要望・ご希望がございましたら、「2025年テーマリクエスト」 と記載の上、以下の【お問合せフォーム】に投稿してください。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
